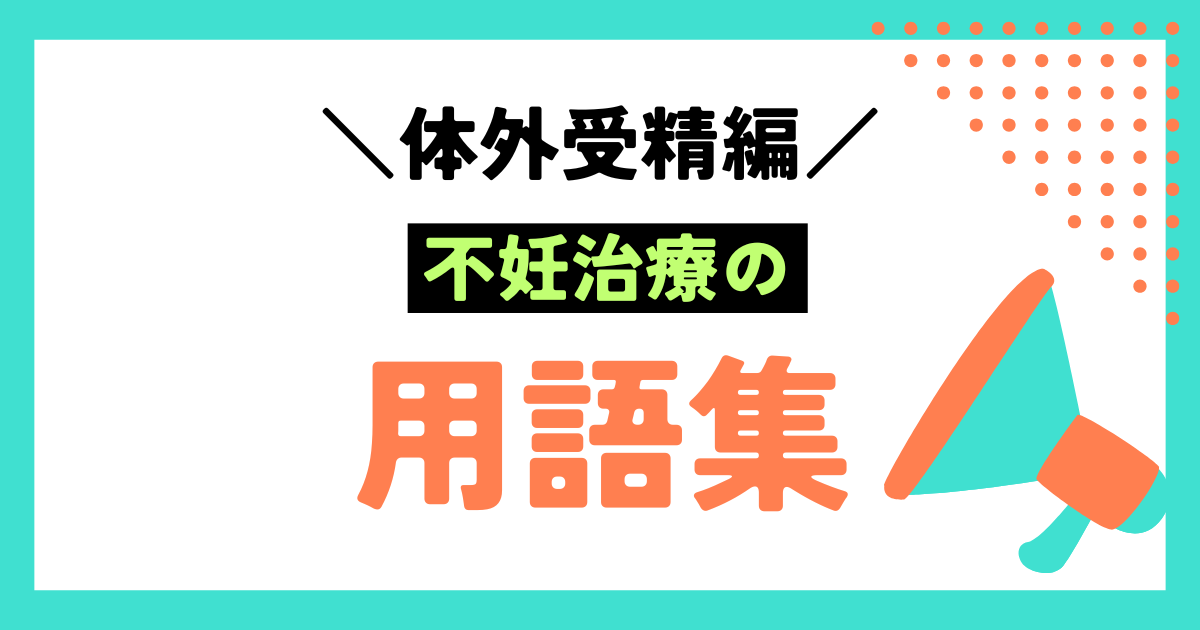
不妊治療の用語集第二弾!
今回は「体外受精編」です。
体外受精へステップアップすると、聞いたことのない専門用語が次から次へと出てきます。
IVF?
ICSI?
ET?
BT?
先生や看護師さんへ質問できればいいのですが、
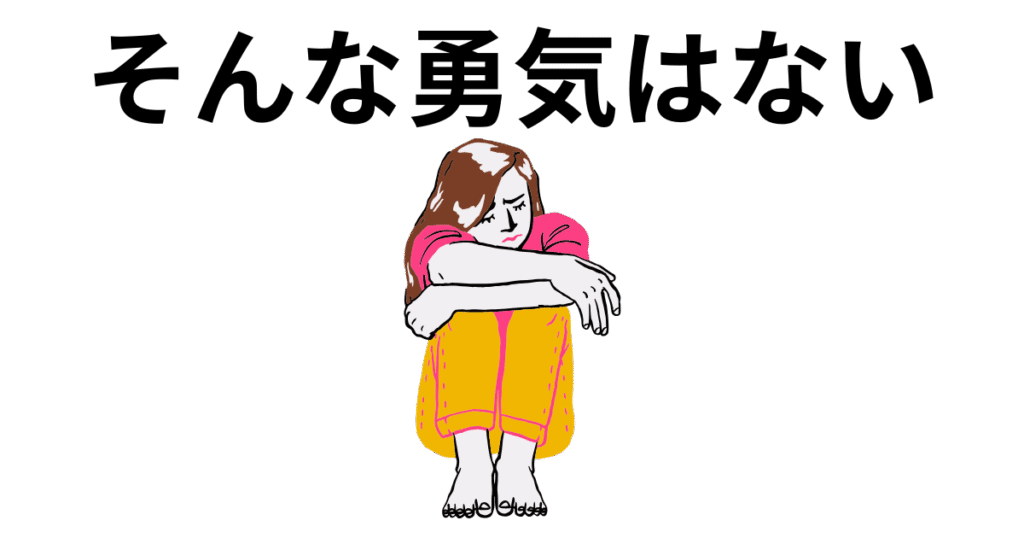
という方は必見です!
この記事では、不妊治療をこれから始める方・始めたばかりの方に向けて、治療の現場でよく使われる専門用語をやさしく、わかりやすくまとめました。
筆者は、不妊治療を5年半経験し、いまは不妊カウンセラーとして活動しています。
「知らない言葉があるだけで、不安になる気持ち」を、私はよく知っています。
この記事が、「専門用語に振り回されない安心感」につながることを願っています😊
今回は「体外受精編」!
それでは、体験談とともに体外受精に関する用語をお届けします。
(前回の不妊治療の用語集「検査編」はこちら↓)
目次
1.不妊治療でよく聞く用語
-2-724x1024.png)

ART(生殖補助医療)
正式名称
Assisted Reproductive Technology
ARTは、不妊治療の中でも、医療の力を使って「卵子と精子が出会う・着床する」ことを助ける技術全般のことを指します。
タイミング法や人工授精(AIH)は含みません。
初めてARTと聞いたときは「芸術」を思い浮かべて、なんだかワクワクしたのを覚えています😁
体外受精と生殖補助医療は同じじゃないの?🤔
と混乱していたのですが、
生殖補助医療には
・体外受精
・顕微授精
・胚凍結、移植
なども含まれ、ARTの中に体外受精や顕微授精も含まれるということです☝
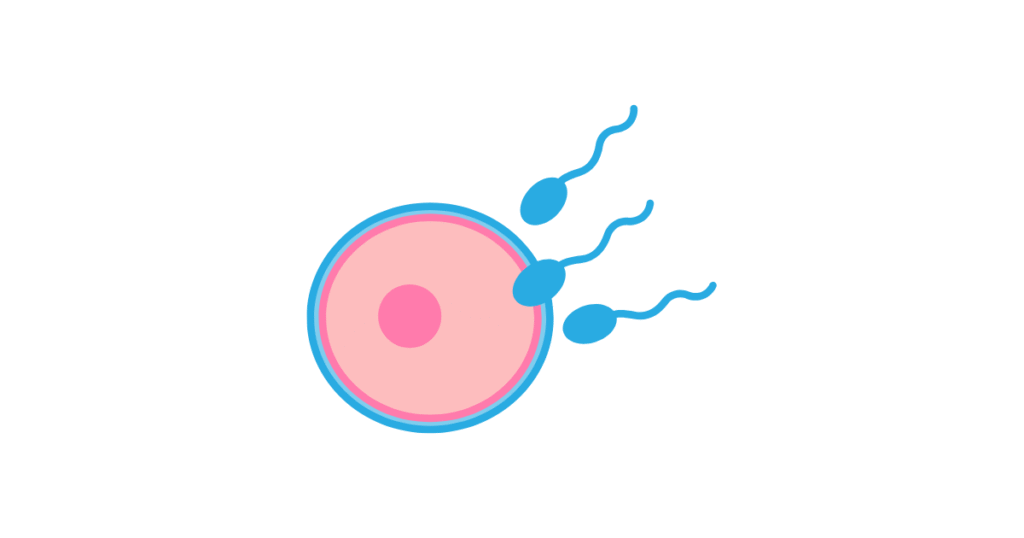
IVF(体外受精)
正式名称
In Vitro Fertilization
卵子を体の外に取り出して、精子と受精させる方法。
受精卵(胚)を培養し、子宮に戻す(移植する)ことで妊娠をめざします。
私は英語が苦手なので、IVFの単語の意味を調べました💡
In Vitro…試験管内で
Fertilization…受精
Vitroの意味だけを調べたので、直接的な単語に少しびっくりしました!(昔は試験管ベビーと呼ばれていたこともあったんですよね)
ちゃんと調べると「体外で」という意味がしっかり理解できましたが、捉え方で印象はかなり変わるなぁと思った出来事でした😌
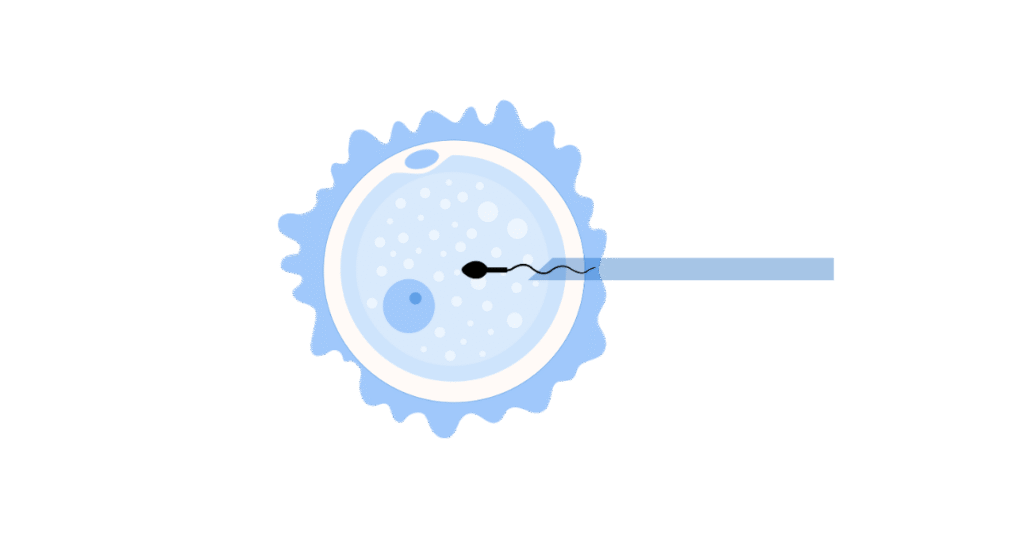
ICSI(顕微授精)
正式名称
Intracytoplasmic Sperm Injection
1つの精子を針で卵子に直接注入する方法。
精子の数や動きが少ない場合などに使われます。
IVFよりも手技が細かく、より高度な技術が必要です。
体外受精と顕微授精で「じゅせい」の漢字がちがうのをご存じでしょうか?
・体外受精(受ける)
・顕微授精(授ける)
ちなみに人工授精も手偏がつきます💡
これは受精方法がちがうからなんです!
受精…卵子と精子が結合して受精卵になること
授精…人工的に精子を注入する行為
こうしてみると、用語を知るのが楽しくなりますね☺
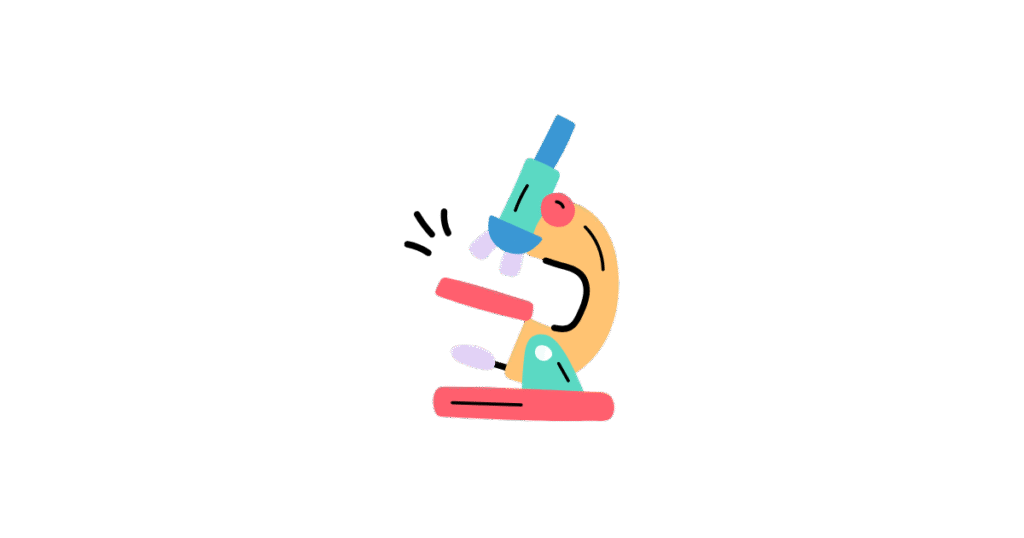
AHA(アシステッド・ハッチング)
受精卵を包んでいる膜(透明帯)を、レーザーや薬剤で薄くして“孵化”を助ける方法。
膜が硬いと着床しにくくなるため、年齢が高い方や胚の質が気になる場合に提案されます。
2022年4月の不妊治療の保険適用開始に伴い、保険適用対象となりました。
私は、毎回移植をするときにはAHAをしていました。
「アハ」と聞くと、なんか気が抜ける~と思っていました🤣(本当にアハと読みます!胚培養士の友人に確認しました)
本で調べると
・透明帯が厚い人
・38歳以上の人
・ART反復不成功の人
・凍結融解胚を移植する人
などに有効と言われています💡
しかし、手技に熟練していない不適切AHAはかえって着床率が著しく低下することもあるそうです。
不安な方は、通院しているクリニックへよく確認してくださいね😌
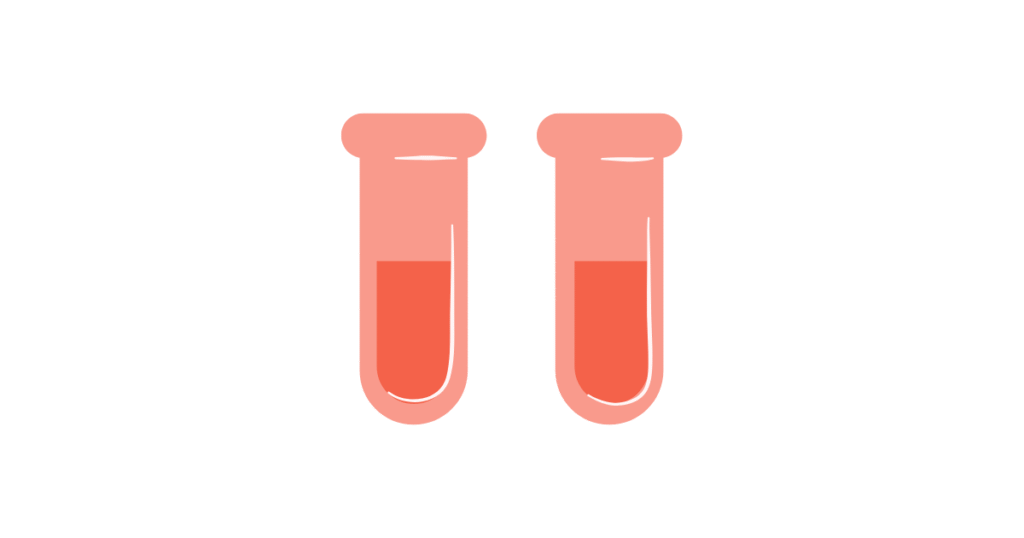
SEET法(子宮内膜刺激術)
胚盤胞移植の前に、胚を培養した培養液を子宮内に注入し、着床しやすい環境を整えることを目的とした方法です。
「着床しやすい子宮環境を先につくる」ことが目的で、“着床のサイン”を子宮に送るイメージです。
SEET法はこんなときに検討されることが多いです。
・胚のグレードが良いのに着床しない
・繰り返す移植失敗
・子宮側の着床環境を整えたいとき
SEET法は先進医療に認定されています☝
私はSEET法も毎回やっていました。
移植の数日前に胚培養液を子宮へ注入するのです。
なんのためにSEET法をするのかが興味深い!(下部の参考コラムをご覧ください)
自然妊娠では、卵管で受精、発育しながら「子宮内膜を整えて」というシグナルを出しているそうです☝
しかし、胚盤胞移植では5~6日間、培養液で育つので
シグナルを子宮へ送れない=子宮内膜の着床準備が不十分
の状態で移植されるそう。
そのシグナルの代わりを、移植前に培養液を注入することで再現しているのです。
なるほど😳
二段階移植という方法もありますが、SEET法には双子など多児妊娠を避けられることがメリットにあります。
参考コラムはこちら

タイムラプス
受精卵を培養中、インキュベーターの中で常に撮影しながら成長を観察する方法。
胚を取り出さずにチェックできるため、胚への負担が少なく、成長の質を細かく判断できます。
タイムラプス(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養)は先進医療に認定されています☝
培養器に入れたまま、カメラで自分たちの受精卵を撮影できるってなんかすごいですよね✨
受精卵を培養器から取り出さず観察できるので、受精卵へのストレスも軽減できるそうです。
ストレスを減らしてあげたい、と思うのは親心ですね☺
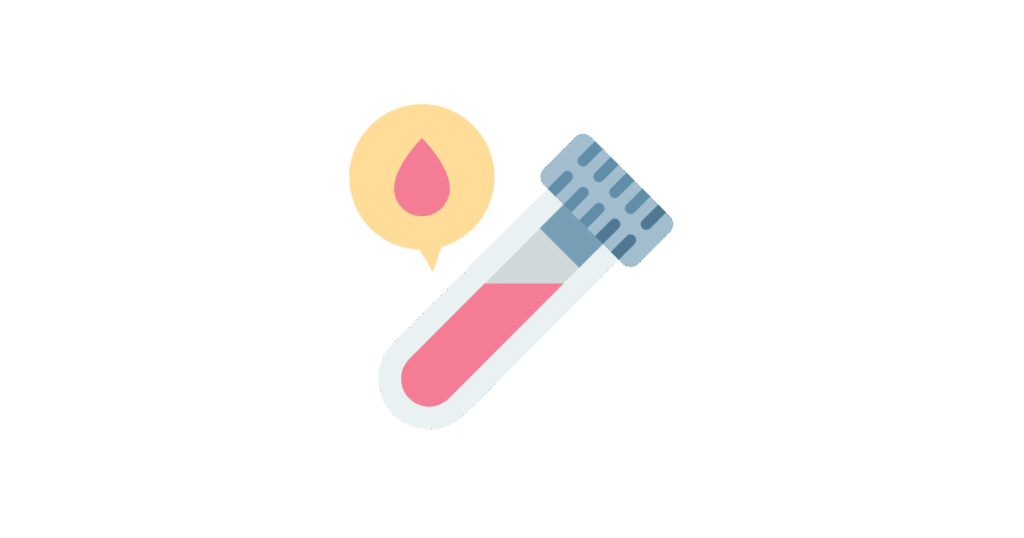
PRP療法(多血小板血漿療法)
自分の血液から成長因子を含む血漿(PRP)を取り出し、子宮内に注入することで内膜を厚くし、着床しやすい状態に整える方法。
子宮内膜が薄い人、移植を繰り返しても着床しない人に提案されることがあります。
PRP療法は先進医療には認定されておらず(2025年7月現在)、PRP療法を行う周期はすべて自費診療となることに注意が必要です☝
私は凍結卵が残りふたつになった時に、PRPを試しました😊
大谷翔平選手が右肘の「靱帯損傷」にPRP療法を行ったと聞いて、「私もやってみよう」と思いました😁
採血をして血漿部分を抽出し、移植の数日前に2回、子宮内へ注入。
痛みもなく、気になったのは通院回数が増えて高額になったことくらいかな。
先生から2ヶ月ほど効果があると聞いたので、2ヶ月連続で移植をしました☺(残念ながら妊娠はせず…)
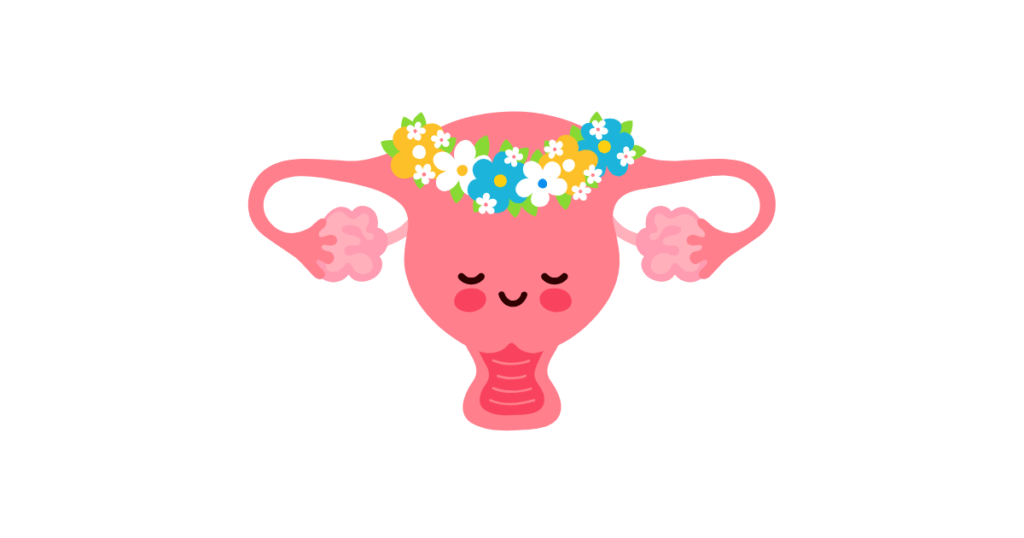
ERA検査・EMMA検査・ALICE検査
ERA・EMMA・ALICE検査は先進医療に認定されています☝
体外受精をする前や、良好な受精卵を移植しても妊娠しない方は検査を受けてみてもいいかもしれません。
ERA検査
子宮内膜が「受精卵を迎え入れられるタイミング(着床の窓)」を調べる検査。
自分に合った着床のタイミングで胚移植を行うことができます。
EMMA検査
子宮内膜に存在する細菌のバランスを調べる検査。
着床にはラクトバチルスという善玉菌が多いことが望ましいとされています。
ALICE検査
子宮内に慢性的な炎症があるか(=慢性子宮内膜炎)を調べる検査。
炎症があると、着床の妨げになる可能性があるため、抗生剤での治療が必要な場合もあります。
私は良好な胚盤胞を2~3回移植しても妊娠しなかったので、ERA・EMMA・ALICE検査をしました。
子宮内フローラが改善されているかを確認するため、合計で3回検査をして、子宮内フローラを30%台から99%まで改善できました🌸
私の場合は検査中の痛みがひどく、検査を受ける前はかなり緊張していました😂
この検査は最初から必要な検査ではなく、繰り返す移植の失敗や原因不明の不妊で悩んでいる方にとって、「わからなかった理由が見えるかもしれない」検査です💡
実際、私はこの検査で
・着床の窓が12時間遅かったこと
・子宮内フローラが乱れていたこと
がわかりました。
それまではどの検査をしてもこれといった原因がわからなかったので、異常がみつかったことはうれしさにつながりました。(異常がわかってうれしいというのも不思議ですが😂)
ただ、移植のタイミングをこれまでから12時間遅らせても、子宮内フローラを99%に改善しても、結果として妊娠することはありませんでした。
原因と思われることを改善しても、妊娠するとは限らないのが妊活。
「きっと検査ではわからないけど、なにかしらの原因があるんだろうな」
と自分に言い聞かせてはいましたが、不安要素をつぶせたという点では、この検査をしてよかったです☺
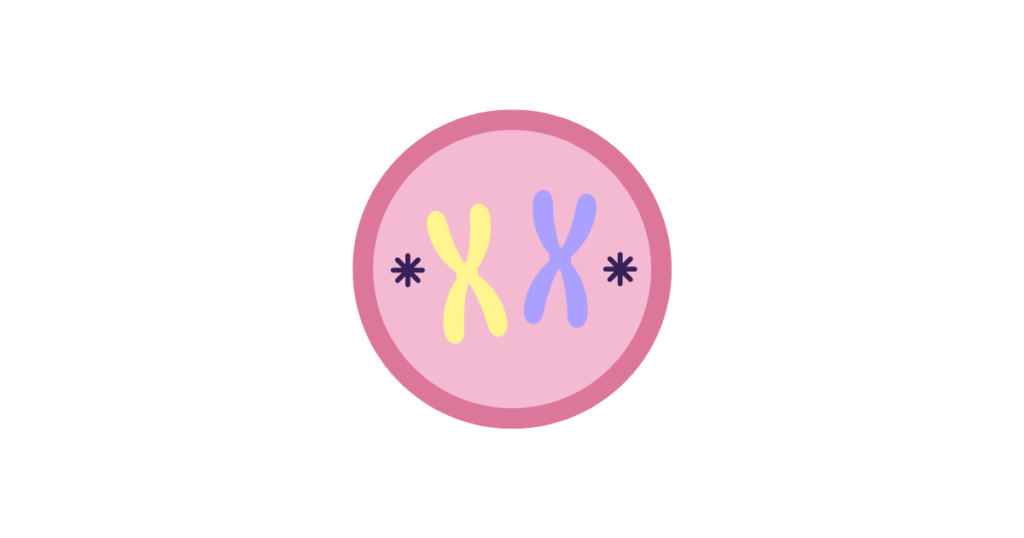
PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)
胚移植の前に、受精卵の染色体数に異常がないか調べる検査。
正常な染色体を持つ胚を選ぶことで、妊娠率の向上や流産のリスク低下を目指します。
PGT-A(着床前胚異数性検査1)は先進医療に認定されています☝
とても興味深い記事を見つけました!
PGT-Aは保険適用外のため、PGT-Aを行うための採卵から胚移植まで、すべてが自費診療となります。(混合診療がNGなため)
PGT-Aを行ったけど移植できる胚がなかった場合は、再度高額な自費での体外受精が必要となり、経済的に治療を諦める(=子どもを諦める)場合もあります。
そこで見つけたのが慶愛クリニック様のコラム!
なんと、保険で採卵できる回数が残っていて、かつ、条件を満たしている患者様は、PGT-A検査の費用をクリニックで負担してくださるとのこと!😳
院長先生の熱い想いに心を打たれました…
患者のことを想ってくれる医療職の方へ、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました😭✨
コラムはこちら
2.不妊治療でよく聞く薬剤
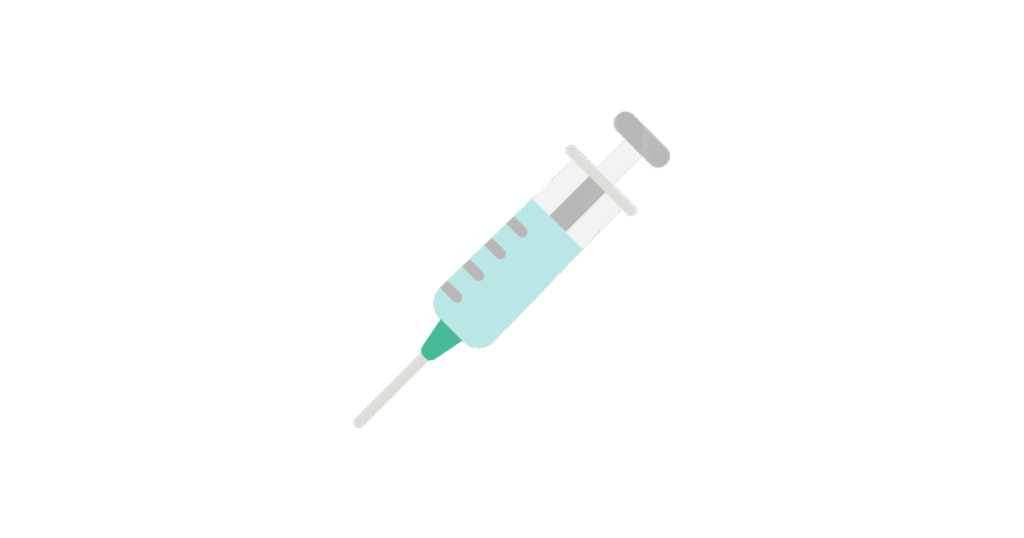
hCG注射
排卵を誘発するための注射。卵胞が育った後、排卵を促したり、排卵のタイミングを調整する目的で使われます。
hCG注射によってLHサージを意図的に起こし、注射を打った後、36~40時間程度で排卵します。
私はhCG注射をクリニックで打ってもらうとき、いつも緊張していました😂
筋肉注射で、苦手な痛みでした…
看護師さんは念入りに腕を揉んでくれて、痛みを軽減してくれていました。
この注射を打つと、今月も頑張るぞー!と気合が入るのでした🔥
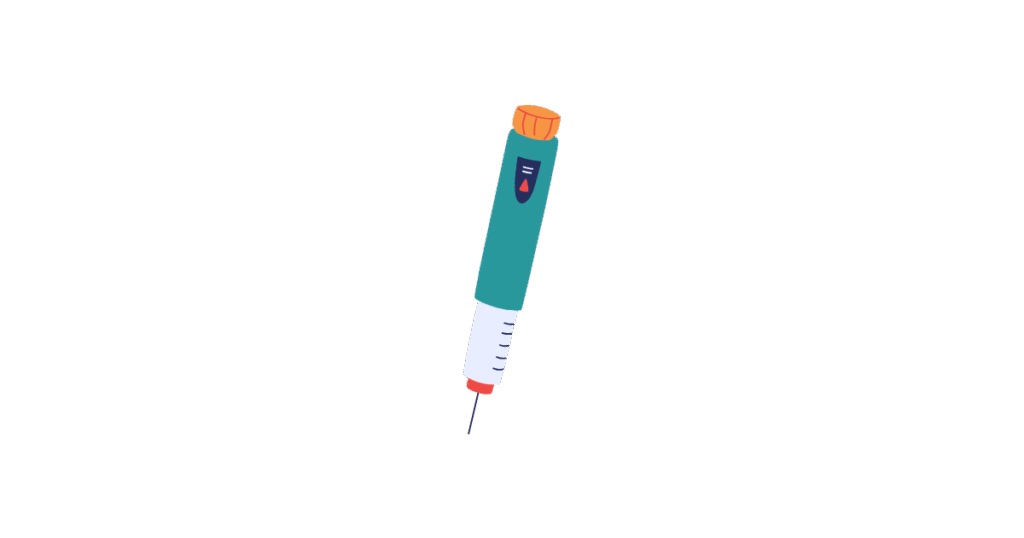
ゴナールエフ皮下注ペン
卵胞刺激ホルモン(FSH)というホルモンを人工的に作った薬で、採卵の周期に複数の卵胞を育てるために使います。
自己注射タイプで、ペンのような見た目が特徴です。
採卵のとき、ゴナールエフ皮下注ペンを使いました。
自分で注射をするって、医療職でない私にとってはドキドキでした!
容量をまちがえないように、しっかりと針が刺さるように、と毎回緊張…
毎回通院するのは大変だったので、自宅で注射できるのはありがたかったです☺
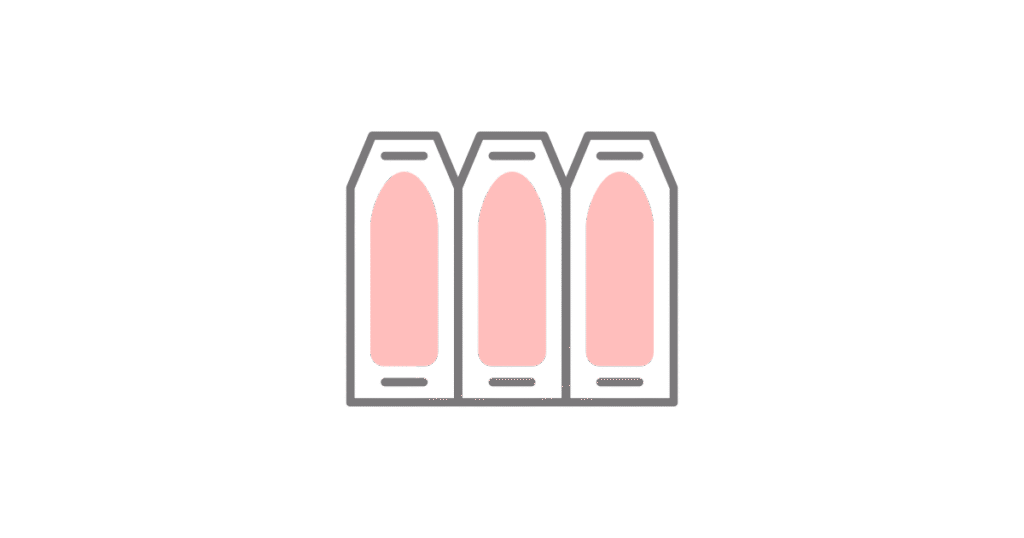
ウトロゲスタン(プロゲステロン補充)
ウトロゲスタンはプロゲステロンを補充するための医薬品であり、プロゲステロンそのものではありません。体外受精や顕微授精でよく使われます。
プロゲステロンは体内で生成される女性ホルモンの一種で、黄体ホルモンとも呼ばれます。排卵後から活発に分泌されます。
- 厚くなった子宮内膜を維持する
- 体温を上昇させる
膣座薬でウトロゲスタンを補充していましたが、膣に座薬を入れたあとに、白いどろっとしたカプセルの薬剤(?)が出てきて、おりものシートが手放せませんでした😂
8時間おきに補充しないといけないのも、けっこうしんどかったです…
私の場合、早寝早起きだったので、補充する時間が0時だったときはつらかったです😭(着床の窓がずれていたので)
移植後は自分の生活サイクルで8時間おきに補充できるようにしてもらいました😌
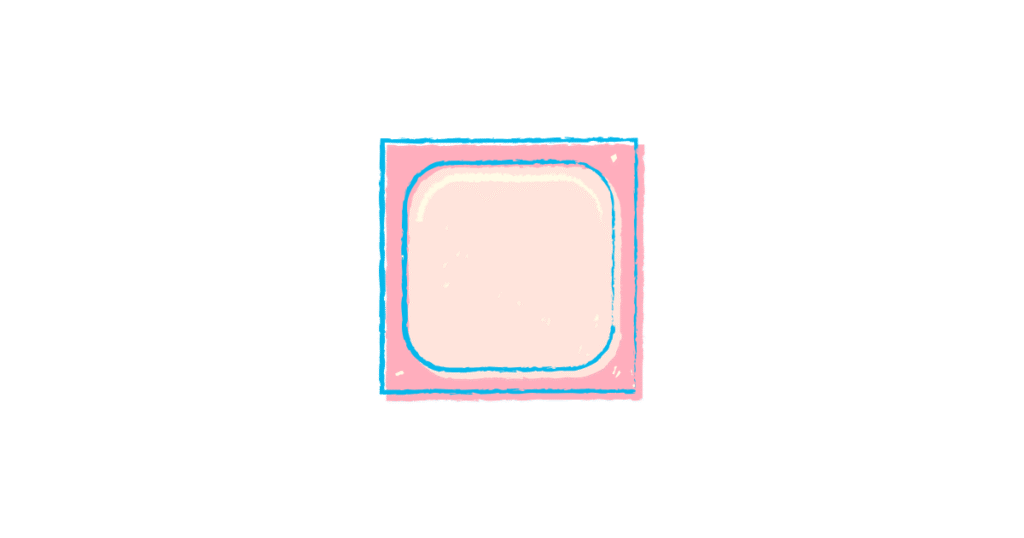
エストラーナテープ
エストロゲン(卵胞ホルモン)を補う貼り薬。
子宮内膜を厚くする目的で、体外受精や顕微授精でよく使われます。
移植に向けてどんどん枚数が増えていくエストラーナテープ。
下腹部はテープでいっぱいになって、貼るところがない、なんてことも😂
私は丸いものが並んでいるのを見るのが苦手なので、なるべくランダムになるように貼っていました☝
かゆみもでてくるので、しっかりと保湿をするのがおすすめです✨
3.ETとBTのちがい
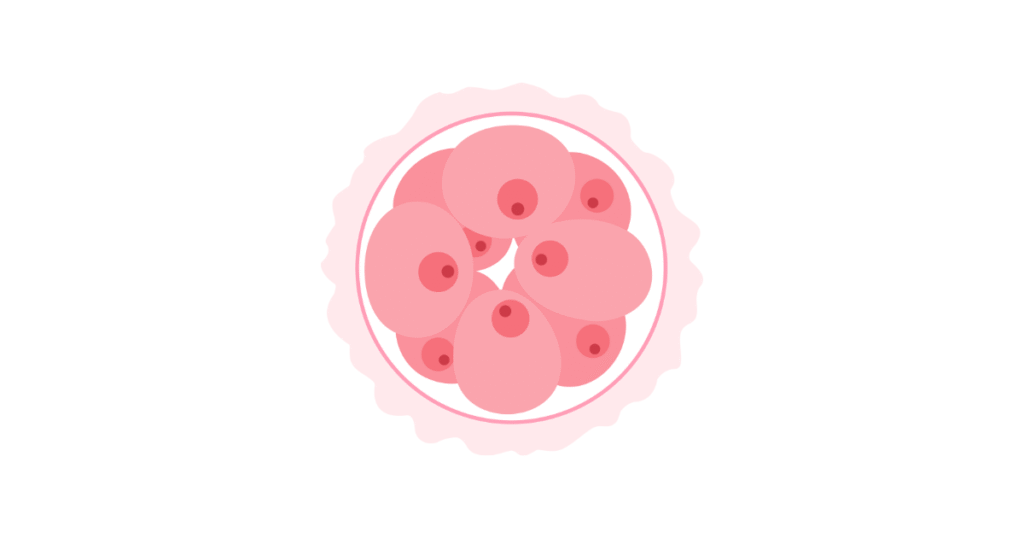
ET(胚移植)
ET:「受精卵を子宮に戻すこと」全体を指す言葉
- Day2(2日目)やDay3(3日目)など、まだ細胞分裂が初期段階の胚を移植する場合も「ET」と呼ばれます。
- 「新鮮胚移植」も「凍結胚移植」もどちらも含みます。
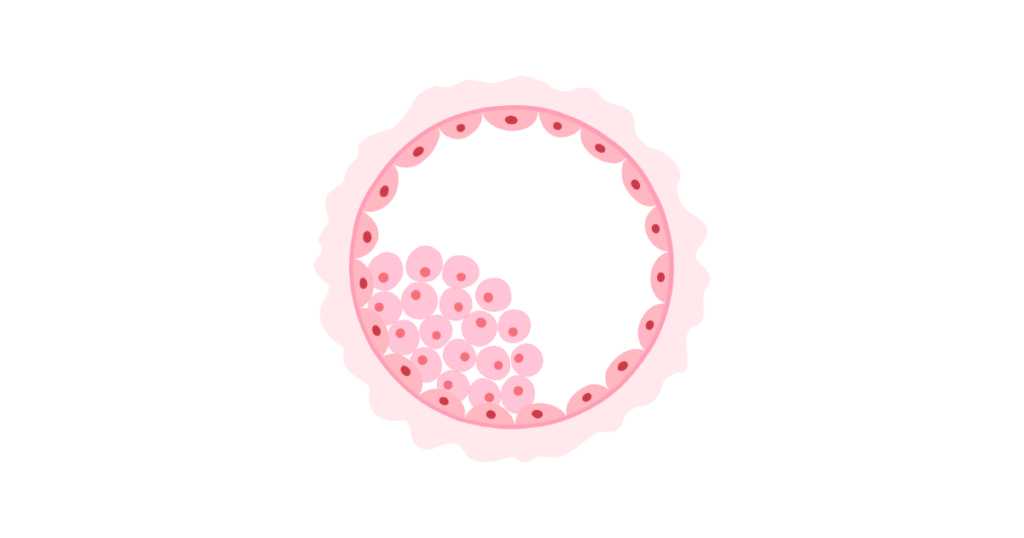
BT(胚盤胞移植)
BT:「胚盤胞(5〜6日目)まで育てた胚」を移植すること
- より自然妊娠に近いタイミング・形に近い胚を戻すので、ETの中でも“より着床しやすい”とされる移植方法です。
- ただし、すべての受精卵が胚盤胞まで育つわけではないため、移植キャンセルのリスクもあるのが特徴です。
つまり、BTはETの一種という関係です💡
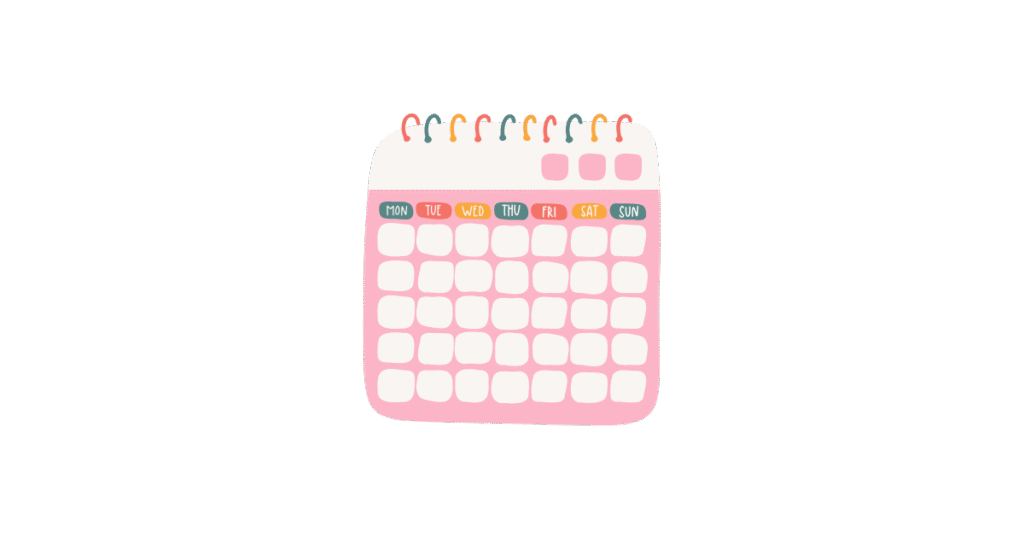
BTの数え方
-3-1024x809.png)
例えば、
BT3=「胚盤胞移植の3日後」=移植から数えて4日目
初めての移植を終えて、「移植 〇日目」と体験談を調べていたときに、「ET」や「BT」と書かれていて、「どうゆうこと?」と思ったことがあります💡
移植周期は一日のずれが大きく影響を与えるようなシビアな気持ちだったので、意味を間違えないように気を付けていました😌
ブログを見ていると、BT7で妊娠判定をしている人がいる中、私のクリニックではBT14で妊娠検査をしていたので、待つ時間がとてつもなく長かったです…

4.迷ったときは
用語がわかるだけで、不妊治療の
「見えないストレス」
を減らすことができます。
でも、全部覚えようとしなくても大丈夫。
大切なのは、自分のペースで理解していくことです。
もし不安な気持ちが続くときは、
一人で抱えずに、話してみてくださいね。
妊+には
不妊を経験したカウンセラーもたくさんいます。
あなたに合ったカウンセラーに相談してくださいね。




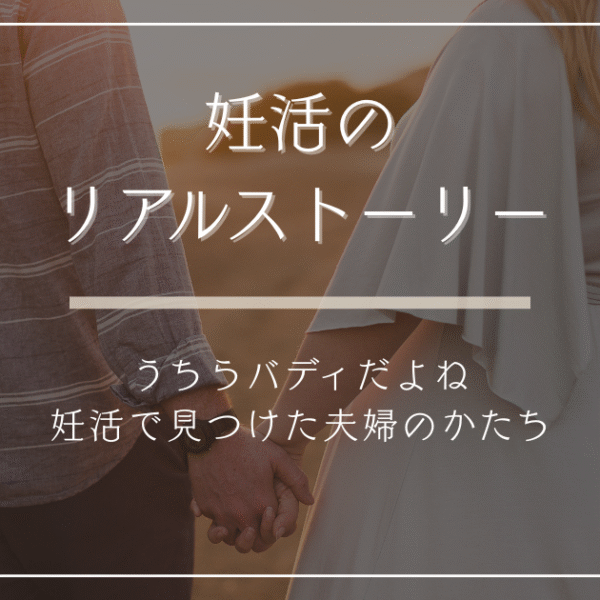

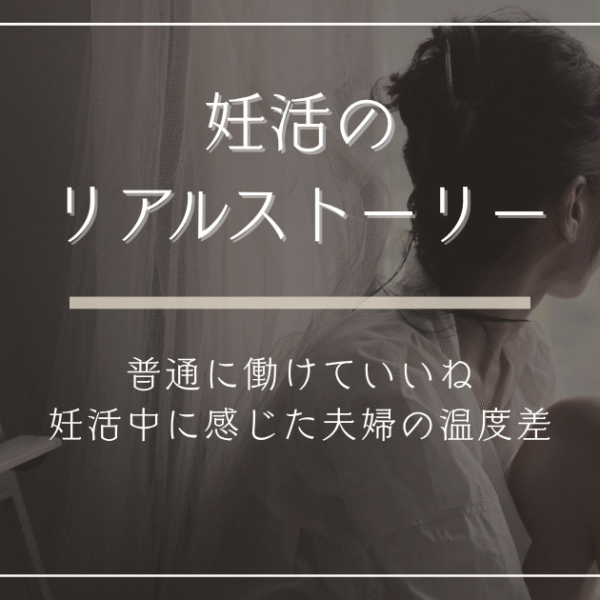

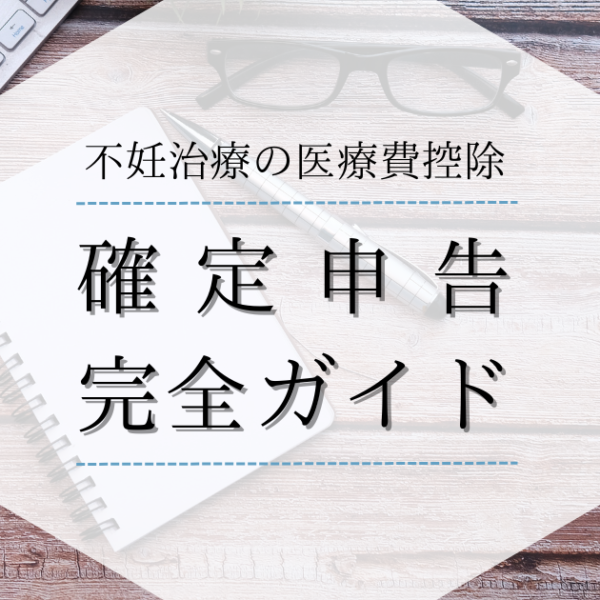


コメント