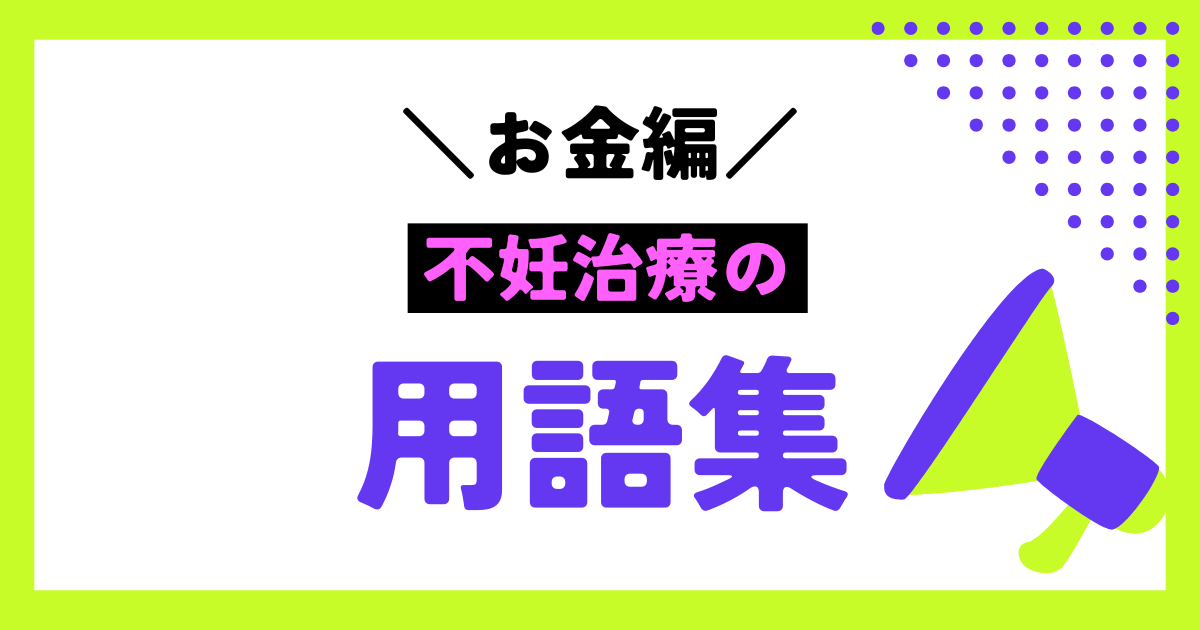
不妊治療の用語集第三弾!
今回は「お金編」です。
保健適用、先進医療、高額療養費制度、医療費控除…
いろんな言葉が飛び交ってよくわからない😱
私自身も不妊治療を始めた当初はお金のことが不安で頭がいっぱいでした。
制度や助成金ってなにがあるの?
そもそもなにを調べたらいいの?
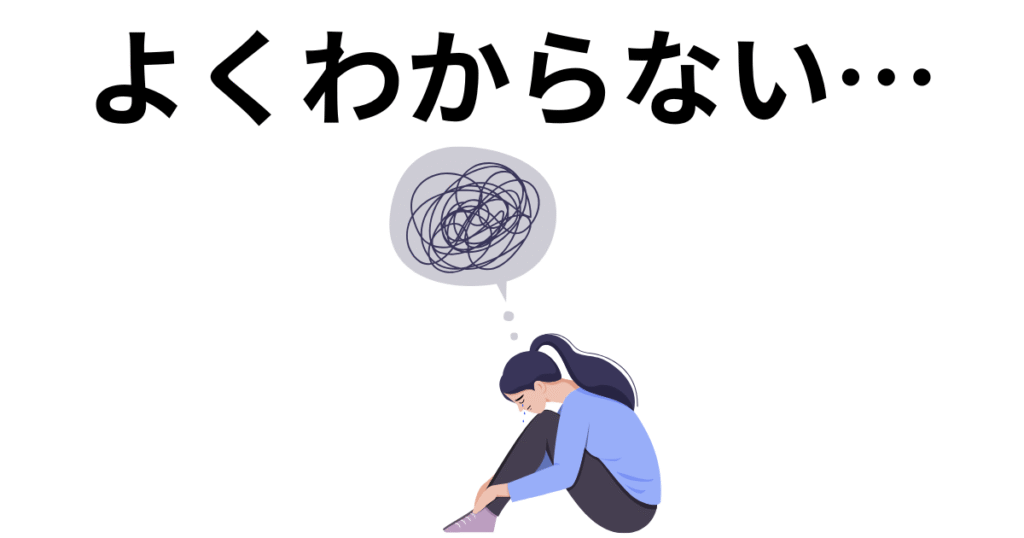
という方は必見です!
この記事では、不妊治療をこれから始める方・始めたばかりの方に向けて、不妊治療費に関する制度や用語をやさしく、わかりやすくまとめました。
筆者は、不妊治療を5年半経験し、いまは不妊カウンセラーとして活動しています。
自分が使える制度を知って、お金の不安を減らして妊活をすすめましょう!
それでは、体験談とともに不妊治療費の制度に関する用語をお届けします✨
(検査編と体外受精編はこちら↓)
目次
不妊治療のお金に関する用語
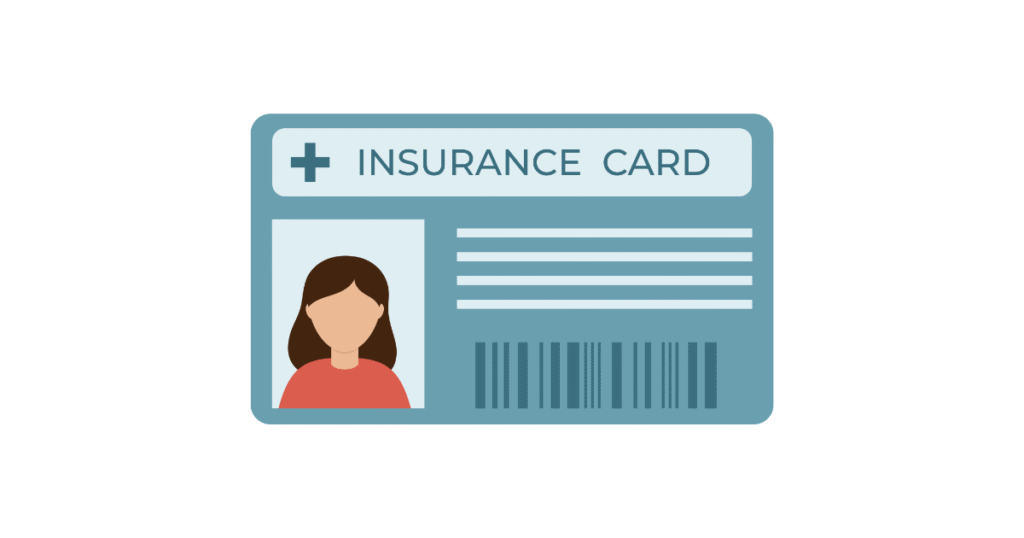
保険適用
2022年4月から、一定条件を満たす不妊治療に健康保険が使えるようになりました。
タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精の一部が対象で、治療費の自己負担は3割になります。
体外受精や顕微授精が保険適用となっていろんな声があがりましたね。
治療費が安くなる人もいれば逆に高額になる人も。
私は一度だけ保険診療で移植をしましたが、これまで使っていた薬が使えなくなって少し戸惑いました。
年齢制限や回数制限についてもいろんな意見があると思いますが、少しずつ不妊治療をしやすい環境が整っている気がしてうれしいです☺
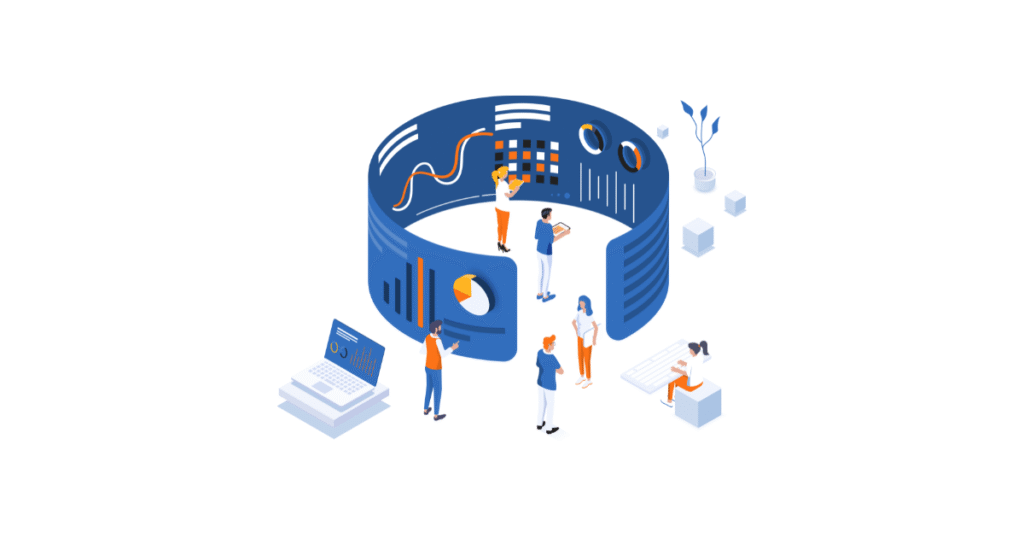
先進医療
厚生労働省が認めた、高度な医療技術を用いた治療です。不妊治療ではタイムラプス培養やERA検査などが該当し、保険と併用できますが、先進医療分の費用は自己負担となります。
クリニックによって受けられる先進医療がちがうのがポイント!
体外受精に進むときは先進医療を利用することも見据えて、クリニックを選ぶのがいいかもしれません💡
厚生労働省のHPに先進医療を実施している医療機関の一覧が掲載されているので最新情報をチェックしましょう!
参考:厚生労働省「先進医療を実施している医療機関の一覧」
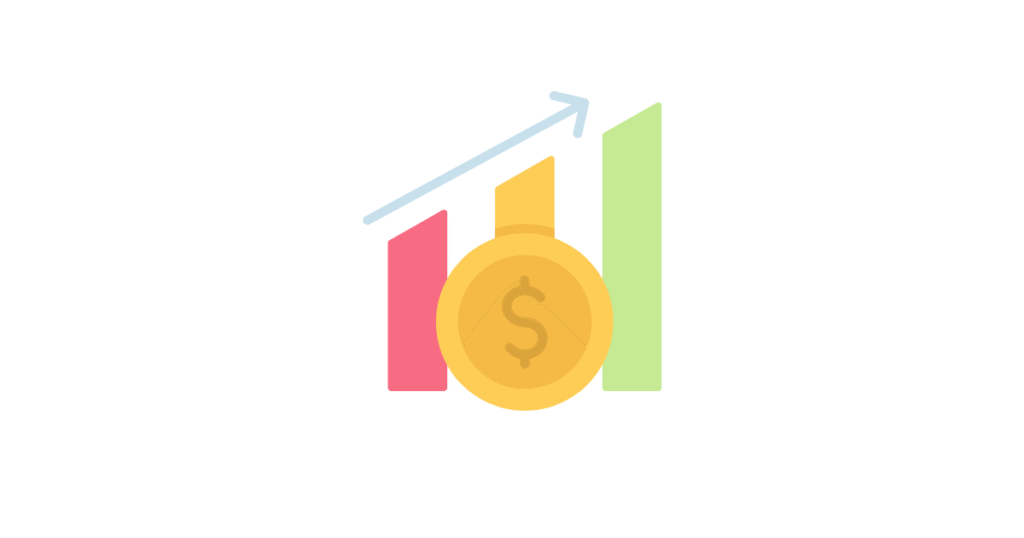
高額療養費制度
1か月の医療費が高額になった場合、自己負担額に上限が設けられており、超えた分が払い戻される制度です。年収や年齢により限度額が異なり、事前の申請で負担を軽減できます。
不妊治療が保険適用になったから利用できる高額療養費制度!
保険適用される診療が対象なので、自費診療での費用は対象外となることに注意💡
1か月の医療費とは1日~末日なので、月をまたいで治療をした場合は払い戻されない場合も😱
厚生労働省のHPで内容をしっかりチェックしてくださいね💪
参考:厚生労働省HP「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
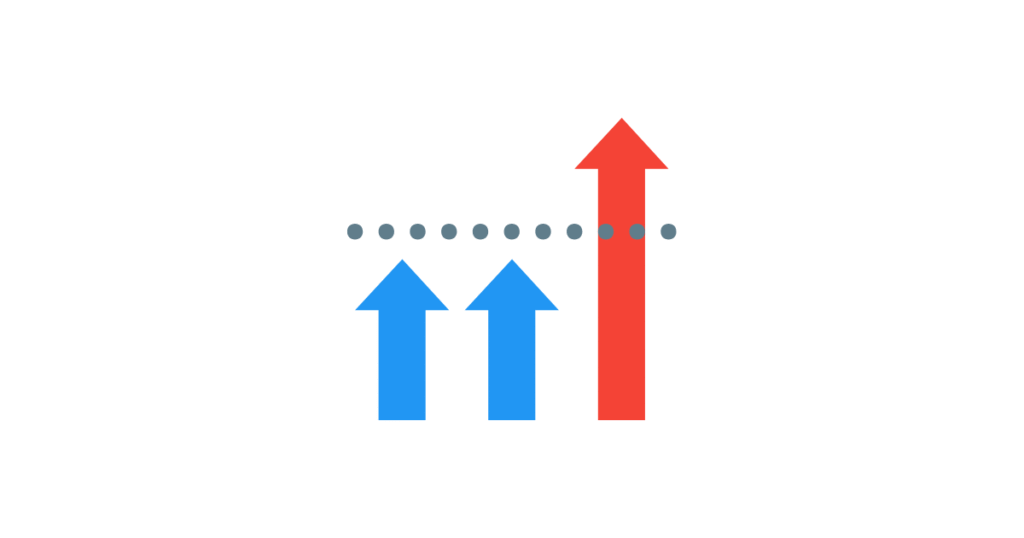
自己負担限度額
高額療養費制度における、ひと月あたりの自己負担の上限額です。収入区分に応じて決まっており、これを超えた分は申請により払い戻されます。入院や手術がある場合に重要です。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
| 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ~年収約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます!
1つの医療機関等での自己負担では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。
この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります👍
参考:厚生労働省HP「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いを、自己負担限度額までに抑えることができる証明書です。加入している健康保険組合や協会けんぽに申請すると取得でき、事前の準備が経済的に有利です。
予め「限度額適用認定証」を交付されていることにより、病院での支払いを高額療養費の上限額までとすることができます☝
私は利用したことはないけど、体外受精で費用がかかることがわかっているなら準備しておくのはアリですね😍
高額療養費制度だと医療費を支払った後に還付なので、そもそも上限までしか払わなくていいのはうれしい!

世帯合算
同じ健康保険に加入する家族の医療費を合算し、高額療養費制度の対象とすることができます。家族それぞれの医療費が少額でも、合算することで負担軽減の対象になる可能性があります。
ぎりぎり高額療養費制度の対象にならない額でも、夫や子どもの医療費を合算して自己負担額を減らせる仕組み💡
ただし、共働きなどで別々の健康保険であれば合算できないので注意!

医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、確定申告により所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。不妊治療費、薬代、通院交通費なども対象となります。
不妊治療をして初めて確定申告で医療費控除をしました!
不妊治療をしなかったら自分で税金の手続きをすることはもっと先だったかも☺
自分の暮らしにかかわる制度を知って手続きをすることはとても大切!
大人の階段をのぼった気がしました😁
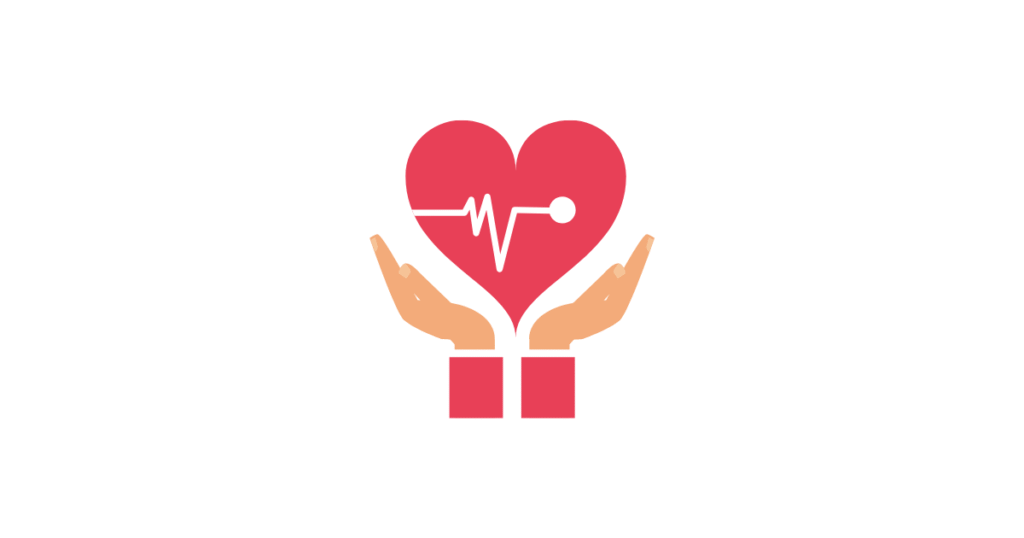
医療保険
民間の保険商品で、病気やけがの治療費に対して給付金が出る保険です。
不妊治療は原則として対象外ですが、入院や手術を伴う場合、対象になることもあり、契約内容の確認が必要です。
保険適用で移植をした周期は、加入していた民間の医療保険から給付金を受け取りました😉
お守りとして加入していた医療保険だけど、給付金をもらえるならもらいたいですよね💡
加入した時期が不妊治療開始後だと告知義務違反になる可能性があるのでしっかり確認しましょう!
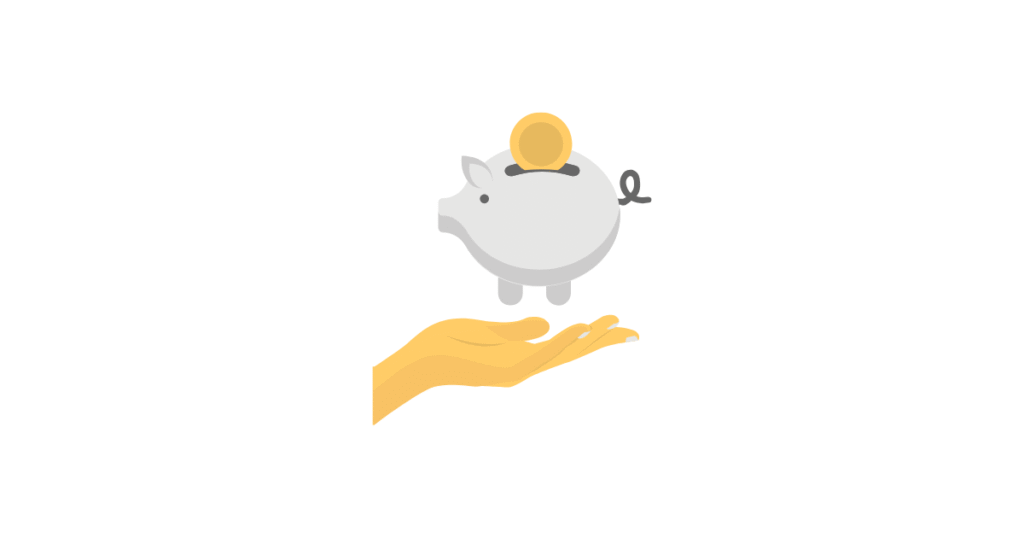
助成金
自治体や政府が実施する、不妊治療費の一部を補助する制度です。保険が効かない治療や先進医療などを対象としたり、所得制限があったりと、内容は地域によって異なります。
助成金は自治体によってさまざまなので都道府県・市町村の両方の情報をチェックしてくださいね☝
申請期限もあるので治療をする前に確認しておきましょう💡

迷ったときは
用語がわかるだけで、不妊治療の
「見えないストレス」
を減らすことができます。
でも、全部覚えようとしなくても大丈夫。
大切なのは、自分のペースで理解していくことです。
もし不安な気持ちが続くときは、
一人で抱えずに、話してみてくださいね。
妊+には
不妊を経験したカウンセラーもたくさんいます。
あなたに合ったカウンセラーに相談してくださいね。







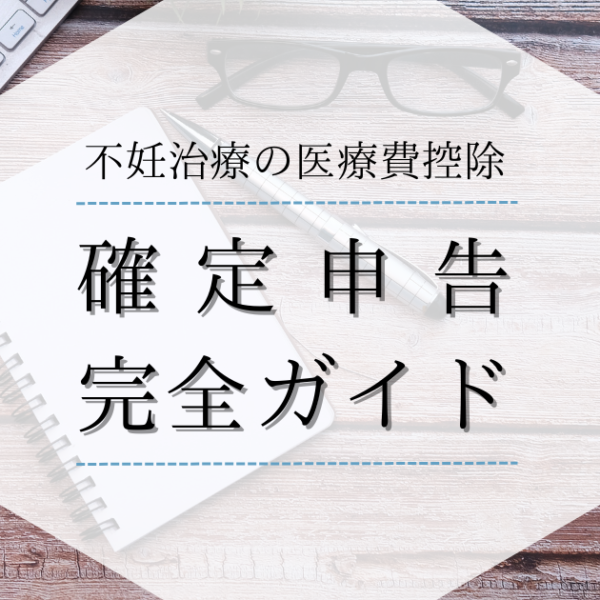
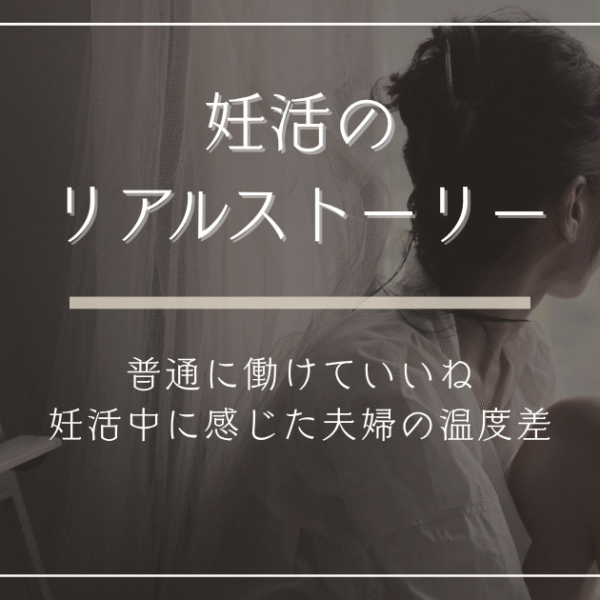
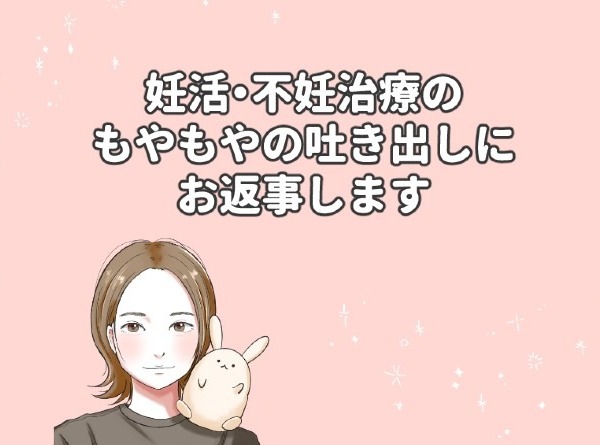

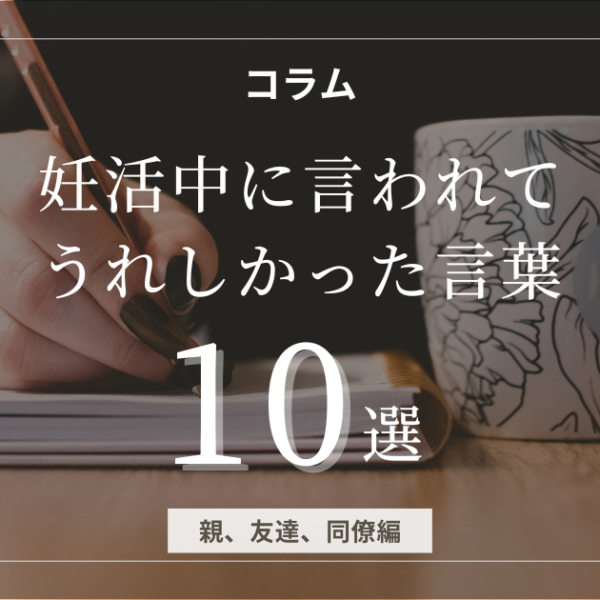

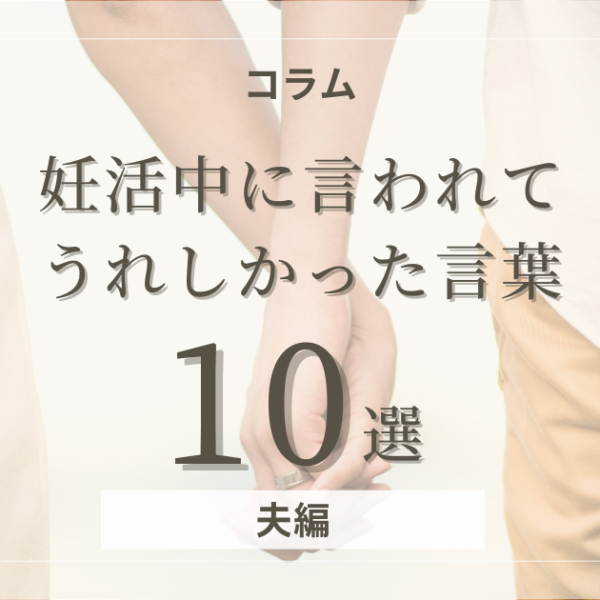
コメント